特許法の概要
特許法とは
特許権は、産業財産権の一つで発明を対象にしたものです。その権利は特許法に保護されています。
特許法:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
- (目的)第1条
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 - (定義)第2条
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
特許法の目的
特許(ライセンス)とは、発明した製品や製法を特許権者が独占し、他者の製品生産や製法利用を禁じることです。
発明には知識やスキルの習得、労力や費用がかかります。特許を申請し特許権を維持するためには費用がかかります。それへの対価として、製品・製法を独占することにより、競争優位に立つことができ、経済的な利益を得る機会を法的に権利として認めるのです。
ロイヤリティ特許権の概念がないと、せっかく発明しても、その成果を他社に利用されたのでは不利ですので、発明しようとする意欲が弱まります。
また、ある発明に刺激されて、他者がさらに高度な発明に挑戦するようになります。その連鎖により、科学が進歩し産業が発展します。発明が秘密にされると、その機会が失われます。
ロイヤリティ
ライセンスを使いたいときは、ライセンサ(特許権者)とライセンシ(実施者、利用者)の間でライセンス契約を結びます。ライセンサは実施権の代金としてロイヤリティ(royalty、特許実施料)を得ることができます。ライセンサが任意のライセンシに実施権を与えることを通常実施権、唯一のライセンシに実施権を与えることを専用実施権といいます。
また、特許権は売買することができます(著作権とは異なり「人格権」に相当するものはありません)。売った後は、売り手は特許権を失います。
特許の対象
特許に相当するのは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう」であり,次の3要件をすべて満足するものです。
- 新規性
- 特許申請時に知られていないこと。論文発表,新聞記事になったものは不可
- 進歩性
- その分野の専門家でも容易に考え出すことができないこと
- 有用性
- その発明が産業の発達に役立つもの
特許法の特徴
特許法と著作権法での違いを下表に掲げます。
著作権法 特許法
目的 文化の発展への寄与 産業の発展に寄与すること
保護対象 著作物(表現) 発明(アイデア)
権利者 著作者 先願者
権利の発生 自動的に発生 審査等の手続が必要
権利の消滅 50年(映画は70年) 20年
権利の維持 無料 特許料が必要
権利の排他性 偶然なら侵害にならない 知らなくても侵害になる
- 権利の発生
- 著作権法では,著作をした時点でなんらの手続をしなくても,著作者の権利が生じます。それに対して特許法では,特許庁による審査・査定が行われ,特許として登録され権利が与えられます。
(日本では、先に特許庁に申請した者に特許権が与えられます。これを先願主義といいます。それに対して、特許申請に関係なく、最初に発明した者に特許権を与える方式を先発明主義といいます。米国は従来、先発明主義を採用していたのですが、現在では先願主義に移行しています。) - 権利の排他性
- 著作権法では,以前にある他人の著作物と同一(類似)の著作物を作成しても,それが偶然になされた(その著作物を見ていないなど)ものであるならば,著作権を侵害したことにはならず,両者が権利を持ちます。
それに対して特許法では,特許があることを知らないで同じ方法で製品を開発して販売したときには特許の侵害となり,それによる損害賠償を請求されます。 - 差止請求権
- 特許が侵害されているとき、あるいは侵害されそうなときに、実施行為(製品の製造など)をを止める権利、しないように請求することができる権利です。
- 先使用権
- いかに先願主義だとはいえ、他社が特許権を得る以前に、その技術を活用した製品を販売していた場合、特許侵害だとされるのは不適切です。特許法では、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施して事業を行っている場合や、その実施のための準備を行っていたような場合には、特許権者の許可なく当該発明を実施することができるとしています。
- 特許異議の申立て
- 発明者以外の者がその発明を知って、先に申請して特許権者になるのは困ります。また、新規性などが疑わしいものもあります。それらを防ぐために、出願から登録の間あるいは登録されてからも,他者(関係者以外でもよい)から特許に対する異議申し立てをすることができます。
国際特許
ある発明に対して特許権の審査基準は、各国の特許法により異なります。原則として、特許権は国内だけに有効で、外国でも特許権を主張するには、直接、その国に特許出願をしなければなりません。
近年は経済と技術の国際化が進み、多数の国で特許権を取得する必要があり、手続きが煩雑になります。それを解消するために特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)があり、その加盟国同士では一つの出願で有効になります。
特許戦略
特許は、競争優位の確保のために、特許戦略を経営の観点からマネジメントする必要があります。特許部門をもつ企業もありますし、その分野の国家資格者である弁理士を活用することもあります。
- 自社優位性の確率
- 特許を持つ技術分野で、他社とのアライアンス(連携)を協議するときに、特許の保有が交渉を優位にします。
ライセンス契約によるロイヤリティの利益が得られます。 - クロスライセンス
- 発明を製品に具体化するには、複数の発明を組み合わせる必要が発生します。このとき、複数の特許権者同士がそれぞれの所有する権利に関して,相互にその使用を許諾することが行われます。これをクロスライセンスといいます。これを効果的に行うには、自社特許だけでなく、他社の特許を調べて製品化のための周辺技術の特許を検討することも必要です。
- 防衛特許(参入障壁)
- 他社がこの分野に参入しようとするとき、特許抵触を避けるには、劣った技術を使うか新技術を開発しなければならず、大きな障壁になります。すなわち、自社業務への他社参入を未然に防ぐことができます。
他社の特許を阻止する戦略もあります。新規性の確認のために、申請された特許を公開して他社の先行利用による異議申立てができます。しかし、その先使用権を主張するには、証明資料の作成や裁判対策など面倒な作業が求められます。それを回避するために、一応特許を出願しておき防御するほうが簡単です。また、早期に特許を申請して、潜在的な模倣者を排除することができます。しかし、特許申請数の増大により、審査期間が長くなる原因になります。 - サブマリン特許(潜水艦特許)
- 発明技術が他社で広く使われるようになってから、特許をもつことを理由に権利侵害を訴えて多額なロイヤルティを請求すれば、大きな利益が得られます。出願後の審査期間に明細書の修正を繰り返すなどにより、わざと特許の成立を遅らせ、普及した頃を見計らうという策略を講じます。
このような手段はフェアとはいえません。防止するために、審査期間の短縮が求められています。
特許ポートフォリオ
特許戦略を進めるには、既保有の特許、計画している特許など、多数の特許について分類し、関連付けを行い、自社の経営方針、技術動向、他社動向など多様な観点から評価することが必要です。
企業が保有や出願している特許を,事業への貢献や特許間のシナジー,今後適用が想定される分野などを分析するためにまとめたものを特許ポートフォリオといいます。
特許ポートフォリオの図式化は、PPMなどと異なり、一般的な形式はありませんが、特許庁「知財戦略事例集」2007年では、ある事例として、次の図表を示しています。
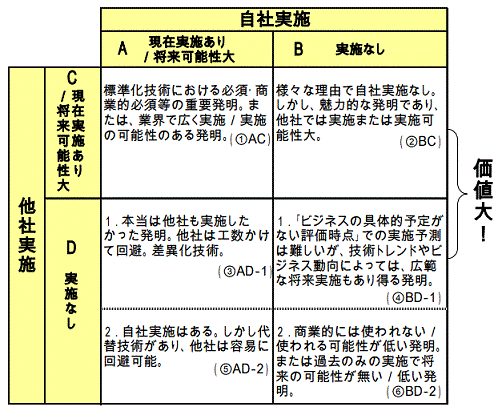
話題になった特許
ソフトウェア特許
自然法則を利用していないものや自然法則そのものは特許の対象にはなりません。それで数学公式やアルゴリズムは、原則として特許の対象にはならないのですが、コンピュータなどと結びつけることにより特許になることがあります。
- 「カーマーカー法特許」ベル研究所 1984年
- これは線形計画法を高速に解くアルゴリズムです。にベル研究所のカーマーカーにより米国で出願され成立,日本でもAT&T社から「最適資源割当て方法」として出願され成立しました。発明の一部は純数学的なものであるが,コンピュータという自然法則を利用しているとして特許になったのです。
- 「GIF特許」ユニシス 1994年
- GIFは有名な画像圧縮方式です。ユニシス社は、1985年にLZW圧縮法の特許を取得していました。CompuServeはその技術を利用したGIF形式の画像データを推奨し、Webページに広く使われるようになりました。1994年に両者間でライセンス契約が結ばれるとともに、GIF画像作成ソフトに特許料を課すことになり、大きな問題になりました。しかしその後、延長申請をしないことになり、特許は失効しました。
ビジネスモデル特許
Webサイトを用いた販売やポータルサイトなどは,有効性の高いビジネス上のアイデアですが,自然法則ではないし,インターネット以外では以前から行われていたのですから新規性に疑問があります。
ビジネス関連での「発明」が,自然法則を利用しているとされる場合としては,「ソフトウェアとハードウェア資源とが協同した具体的手段によって実現されている」ことが必要になります。また,進歩性があるためには,ビジネスとコンピュータ技術の双方の知識を持つ者でも容易に思いつかないものであることが求められます。
有名なビジネス特許として、次の3つがよく紹介されています。これらと同様な仕組みは、多くのサイトで用いられていますが、これらの特許を用いているのか、独自の方法を用いているのか私は知りません。
- 「ショッピングカート特許」オープン・マーケット・インコーポレーテッド、1998年
- 販売サイトで購買者は購入商品をショッピングカートに入れておき、購入手続きはカートの中身全体を一度で行えばよく、個々の商品について行う必要がないというものです。
- 「逆オークション特許」プライスライン・コム,1998年
- 買い手が価格や希望条件を提示して,仲介人が複数の売り手に見積もりを依頼し,選択したものを買い手に提示して取引が成立するというシステムです。このような取引方法は実社会では以前から行なわれていたのですが,それをインターネットで行なうためのハードウェアなどと組合わせることにより特許になりました。
- 「ワンクリック特許」 アマゾン・コム,1999年
- 顧客がインターネットで商品を注文するとき,初回にはクレジットカード番号や個人情報を入力しますが,次回からは,それを記録したクッキーを用いることにより,入力を簡単にするという仕組みです。これには,進歩性がないのではないかと問題になりました。
なお,日本では,アマゾン・コムが日本での特許出願をする以前にソニーがが同様な仕組みを出願しており審査請求はしなかったので特許として成立はしていません。
日本では,ビジネスモデルそのものに独占権を与えるものではないとされており,同様なビジネスモデルであっても,その実現手段での自然法則の利用が異なれば特許に抵触しないと解されています。しかし,米国ではビジネスモデルそのものが特許になるなど,国により異なることがあります。