デジタル庁設置以前の経緯
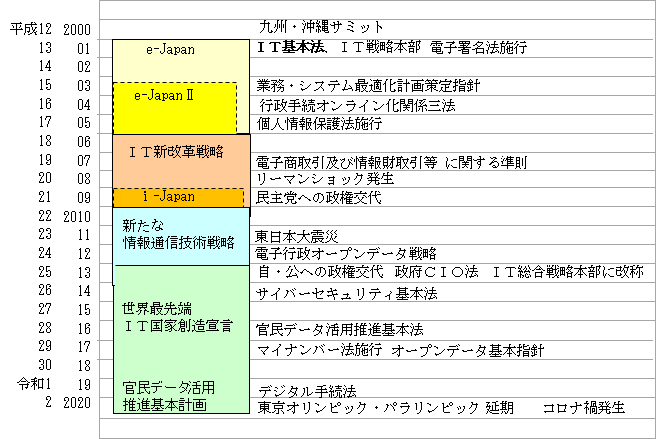 |
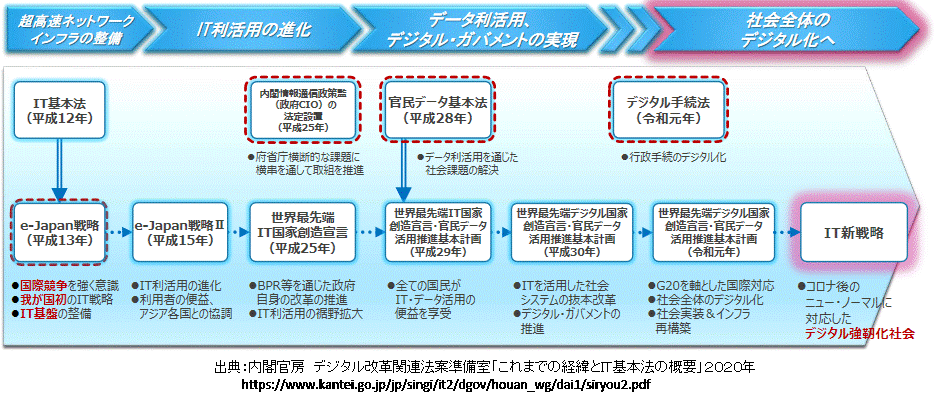 参照:内閣委員会調査室「IT政策の経緯 -「デジタル庁」の議論を見据えて-」(立法と調査 2020. 12 No. 430) |
| 戦略名 | IT基本法 | e-Japan戦略 | e-Japan戦略Ⅱ | IT新改革戦略 | i-Japan戦略2015 | 新たな情報通信技術戦略 | 世界最先端IT国家創造宣言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表年月~目標年 | 2000年11月制定,2001年1月施行 | 2001年1月~2005年 | 2003年7月~2005年 | 2006年1月~2010年 | 2009年7月~2015年 | 2010年5月~個別設定 | 2013年6月~2020年 |
| 特記事項 | 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関して以下を定めた法律 ①基本理念及び施策の策定に係る基本方針 ②国及び地方公共団体の責務 ③IT戦略本部の設置 ④重点計画の作成 |
IT戦略本部による横断的主導体制の確立 IT基本法実現への第1次5ヵ年計画 |
e-Japanのほぼ達成した分野を削除し重点をさらに具体化 | e-Japan戦略Ⅱ路線の発展 | リーマンショック後の経済危機に対応して前倒し 策定直後に民主党へ政権交代により実効を得る前に見直し |
考え方や表現は異なるが、主要分野は前戦略と大差なし 3年後に自・公に政権交代により長期計画は次戦略で見直し |
アベノミクス実現の一環として閣議決定 2020年の東京五輪を見越した長期計画 |
| 達成目標 | 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進する | 5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す | ITの利活用による、元気・安心・感動・便利な社会の実現を目指して | いつでも、どこでも、誰でもITの恩恵を実感できる社会の実現 | 国民主役のデジタル安心・活力社会の実現を目指して | 新たな国民主権の確立 | 閉塞を打破し再生する日本へ 世界最高水準のIT利活用社会の実現 |
| 重点分野 | 基本方針 ①高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進 ②世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 ③教育及び学習の振興並びに人材の育成 ④電子商取引等の促進 ⑤行政の情報化 ⑥公共分野における情報通信技術の活用 ⑦高度情報通信ネットワークの安全性の確保等 ⑧研究開発の推進 ⑨インフラ ⑩安心できるIT社会 ⑪高度IT人材 ⑫人的基盤づくり ⑬研究開発 ⑭国際的な協調及び貢献 |
①超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策 ②電子商取引と新たな環境整備 ③電子政府の実現 ④人材育成の強化 |
○先導7分野 ①医療 ②食 ③生活 ④中小企業金融 ⑤知 ⑥就労・労働 ⑦行政サービス ○新しいIT社会基盤 ①次世代情報通信基盤 ②安全、安心な利用環境 ③研究開発 ④IT人材、学習振興 ⑤国際関係 |
①医療 ②環境 ③ITによる安全・安心な社会 ④ITS(高度道路交通システム) ⑤電子行政 ⑥IT経営 ⑦豊かな生活 ⑧ユニバーサルデザイン社会 ⑨インフラ ⑩安心できるIT社会 ⑪高度IT人材 ⑫人的基盤づくり ⑬研究開発 ⑭国際競争力 ⑮国際貢献 |
○3大重点プロジェクト ①電子政府・電子自治体 ②医療 ③教育・人材 ○産業・地域の活性化及び新産業 ○デジタル基盤の整備 |
①国民本位の電子行政の実現 ②地域の絆の再生 ③新市場の創出と国際展開 |
①革新的な新産業・新サービスの創出及び全産業の成長を促進する社会 ②健康で安心して快適に生活できる世界一安全で災害に強い社会 ③公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会 |
以降の見出しで赤色は国のIT戦略の中長期計画(IT総合戦略本部策定)、紫色は法律、黒色はIT総合戦略本部策定の関連計画および関連事項です。ほぼ年代順に掲げています。
2000年代
2000年頃の状況
インターネットに代表される情報通信技術の急速な発展は。広い分野に多大な影響を与え、IT革命といわれるようになり、高度情報化社会の実現が到来するといわれました。
とりわけ、経済分野では、この動向への対応が企業の国際競争力に与える影響が大きいことが指摘されました。1980年代中頃まで、日本の国際競争力は「Japan as No.1」「21世紀は日本の時代」とまでいわれました。それが1988年頃からのバブル崩壊やそれに続く平成不況により、日本経済は急速に低下しました。そのため、IT革命に乗り遅れ、国際競争力は急速に低下してしまいました。
この状況を打破するために、国は、積極的なIT推進政策を策定・推進することになりました。
参照:2000年頃の状況
IT基本法(2000年成立)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000144正式名称を「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」といいます。高度情報通信ネットワーク社会とはITの高度な利活用による高度情報化社会のことです。
IT基本法では、高度情報化社会のあるべき姿と、その実現のための重点分野を示し、その積極的な推進が国や自治体の責務であるとしました。
そして、これらの施策を各省庁の垣根を越えて、総合的な中長期戦略を策定し推進するための司令塔として、内閣官房のなかに内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)を設置しました。
参照:IT基本法
e-Japan戦略(2001年策定)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai1/1siryou05_2.html
IT基本法により設置された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)は、2001年1月に第1次中長期戦略ともいうべき、「e-Japan戦略」を取りまとめました。
IT基本法の目的を実現するために,「2005年までに世界最先端のIT国家となる」ことを目標に,重点5分野を掲げました。
・世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成(ブロードバンドの普及)
・教育及び学習の振興並びに人材の育成(小中高校でのIT教育、高度IT人材の育成)
・電子商取引の促進
・電子政府・電子自治体の実現
・高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保
この戦略は、PDCAによるローリングプランとして、毎年、進捗状況を報告し重点計画を見直すことになっており、その後の中長期戦略もこの制度を継続しています。
参照:e-Japan戦略
e-JapanⅡ戦略(2003年策定)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030702ejapan.pdf
e-Japan戦略の中頃になると、ブロードバンドの普及、通信料金の低廉化などは、目標を超えて達成されました他の重点分野では、基盤整備だけではなく、それらの成果を享受するには利活用の面を重視するべきだとされました。
それで、e-Japan戦略を全面的に見直してe-JapanⅡ戦略が策定されました。
「ITの利活用による「元気・安心・感動・便利」社会を目指す」ことをキャッチフレーズに「IT基盤を活かした社会経済システムの積極的な変革」を行うとしています。
そのために、「先導的取り組み」として、医療、食、生活、中小企業金融、知、就労・労働、行政サービスの7分野と、それを支える5つの「新しいIT社会基盤整備」を掲げました。
参照:「e-JapanⅡ戦略」
e-Japanの達成状況
- ブロードバンドの普及と価格削減は計画とり短期間で達成しました。
- 電子商取引の分野では、個人の電子決済(BtoC)は遅れていますが、企業間(BtoB)では、規模でもEC化率でも米国を上回る状態びなりました。この当時は国もBtoBを重視してので、成功といってよいでしょう。
- 初等教育(小中高)での情報科目の正規科目化は計画通り実現したが、教員のスキルが不十分で、内容もパソコン操作レベルである。大学教育では産業界のニーズとのミスマッチが多いことが指摘されました。IT関連の修士・博士の数は増加しているのだが不十分です。
- 官民接点のオンライン化では、行政情報のWebサイト開設はほぼ完全達成しました。申請の電子化もシステム開発数としては満足できるレベルに達しました。しかし、利用度が非常に少ないシステム、操作が複雑なシステムが多く、国民IDとした住民基本台帳カードもほとんど普及していない状況です。すなわち国民の立場でのシステムではいとされました。この批判は、この後も長く続きます。
このように、ハード的な分野や数値合わせ的な分野ではほぼ達成しました。国際競争力も挽回の傾向にあります。しかし、政府やビジネスの効率性などITを用いたBPRの分野は低迷している状況です。
参照:e-Japanの達成状況
IT新改革戦略(2006年策定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/060119honbun.pdf
ITの構造改革力の追求として、次の項目と施策を掲げています。
・医療:レセプトの100%オンライン化
・環境:ITでエネルギーや資源の効率的な利用
・災害対策:地上デジタルによる災害情報提供
・交通:ITS(高度道路交通システム)の活用
・電子政府:オンライン申請率50%達成
・産業:ITによる部門間・企業間連携の強化
・生活;テレワーク、e-ラーニングの活用
これらの実現のための基盤整備として、次の事項を掲げています。
・ユニバーサルデザイン、デジタル・ディバイド
・不正アクセス等サイバー犯罪
・人材育成:高度IT人材育成機関の設置等
・研究開発、世界への発信
eーJapan戦略では、IT革命の動向にキャッチアップして海外諸国に追いつけ追い越せという観点から、総花的なアプローチであった感じがします。それに対してIT新改革戦略では、情勢にあわせ、各官庁の政策に合わせた視点から重点を絞り込んだ感じがします。
全般的に、非IT分野の戦略・計画との連携が成否につながる項目が多くなってきました。批判が多かった電子行政では、「世界一便利で効率的な電子行政」とし、システム開発から利用率の拡大に軸足をシフトしてきました。
参照:「IT新改革戦略」
電子行政への批判(2009年頃)
「形は作っても中身が伴わない」との指摘が強くなってきました。全般的には、府省庁横断的なアプローチ不足、既存の制度や法律の壁を越えたBPRの不在などが指摘されています。オンライン申請システムでは、開発から利用率へと方向転換したはずなのですが、その成果は見られませんでした。
このような状況から、電子行政のあり方を見直そう、IT戦略本部のガバナンス能力を強化するための仕組みが必要だとの指摘も出てきました。
参照:「電子行政への批判」
2010年代
i-Japan戦略2015(2009年策定)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/090706honbun.pdf
副題は「~国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実現を目指して~ Towards Digital inclusion & innovation」です。
「国民主役」が大前提になりました。国民のニーズを重視し、オンライン申請なども利用者の立場で考えるべきだとういうことです。inclusion とは「包含」、innovation とは「革新」の意味です。各府庁・地方自治体・民間を統合した立場で革新を行おうという意味で「i-」としたのでしょう。
これらのことは当然であり、以前の中長期戦略も同じだと思いますが、これを冒頭に掲げることにより、戦略の性格を示したのでしょう。
「IT新改革戦略」の最終年度は2010年でしたが、2008年に発生したリーマンショックに続く深刻な経済危機に対応するため、前倒しにしたものです。
1 三大重点分野
(1) 電子政府・電子自治体分野
(2) 医療・健康分野
(3) 教育・人財分野
2 産業・地域の活性化及び新産業の育成
3 デジタル基盤の整備
また、電子政府の推進体制の整備、過去の計画のフォローアップを進めるとともに、2013年までに国民電子私書箱の整備をするとしています。
2009年に、自民党から民主党に政権交代がありました。それに伴い、2010年に「新たな情報通信技術戦略」を策定しましたので、「i-Japan戦略2015」は最終時点の2015年どころか、1年の間に特別な成果を出すことなく消滅しました。
参照:「i-Japan戦略」
新たな情報通信技術戦略(新IT戦略)(2010年)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100511honbun.pdf
2009年8月に、自民党から民主党への政権交代があり、新政権の下で策定された国のIT政策に関する中長期戦略です。
新戦略策定までには時間を要しますので、原口総務大臣は「ICT維新ビジョン」2009、「ICT維新ビジョン2.0」2010を発表、大臣のIT政策を示したものです。「新IT戦略」は、それをベースとしたものになっています。
新IT戦略の特徴は「国民本位」を戦略全体で強調していること、技術やサービスに新しい用語により、これまでの概念を再定義したものがあること、それとともに施策がかなり具体的であることなどが挙げられます。
「政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会への転換」であり、「過去のIT戦略の延長線上ではない」としていますが、政権が交代しても、IT動向やその利活用による高度情報化社会の認識に大きな差異はありません。施策の理念、推進方法、推進体制の違いはあっても、実現すべき重点事項とそれを円滑にする制度などに関しては、以前の中長期戦略の延長線にあるようです。
内容をキーワード列挙で示します。
- ICT維新ビジョン
「光の道」(ブロードバンド普及、法的規制見直し) - 国民本位の電子行政の実現
「国民ID制度」、「公的ICカードの整理・合理化」、「自己情報開示」
「政府共通プラットフォーム」「電子的フォーマット標準仕様」
「e-Gov等の双方化」「地理空間情報、統計調査等の二次加工可能な提供」 - 地域の絆の再生
「どこでもMY病院」「医療情報データベース」
「高齢者、障がい者等に優しいハード・ソフトの開発・普及」「テレワークの推進」 - 新市場の創出と国際展開
「低炭素社会」「スマートグリッド」「人・モノの移動のグリーン化」
「知的財産推進計画2010」「非商業分野におけるデジタルアーカイブ化」「位置情報のコード体系」
:
2013年に、民主党から自民党への政権復帰があり、「新たな情報通信技術戦略」は「世界最先端IT国家創造宣言」に改定されます。
特筆すべきことは、この間に「新たな情報通信技術戦略」の推進に関連する「電子行政推進に関する基本方針」や「電子行政オープンデータ戦略」などが策定され、より実現への路線が固まったことです。
そして、「新たな情報通信技術戦略」の路線は「世界最先端IT国家創造宣言」でもほぼ引き継がれます。
電子行政推進に関する基本方針(2011年策定)IT戦略本部決定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/110803_denshi.pdf
「新たな情報通信技術戦略」(2010年)の大きな柱の一つとして「国民本位の電子行政の実現」を重視しています。それを踏まえて、電子行政の推進理念を抜本的に見直そうとする提言です。
国民の視点に立った、オンライン利用計画、行政サービスへのアクセス向上を推進する。その基盤としての国民ID・企業コードなどの策定・普及をする。情報公開のオープンガバメントなど、府省を横断するガバメントを強化するために、政府CIO制度を設立するなどの施策を進めべきだとしています。
政府CIO制度の提案は、2013年に「政府CIO法」として成立します。
電子行政オープンデータ戦略(2012年策定)IT戦略本部決定
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/120704_siryou2.pdf
「新たな情報通信技術戦略」(2010年)及び「電子行政推進に関する基本方針」(2011年)を受けて、公共データは国民共有の財産であるという認識で、公共データの活用を促進する戦略を示しています。
- 意義・目的
- 透明性・信頼性の向上
行政の透明性の向上、行政への国民からの信頼性の向上 - 国民参加・官民協働の推進
創意工夫を活かした公共サービスの迅速かつ効率的な提供、ニーズや価値観の多様化等への対応 - 経済の活性化・行政の効率化
我が国全体の経済活性化、国・地方公共団体の業務効率化、高度化 - 公開の基本原則
- 政府自ら積極的に公共データを公開すること
- 機械判読可能な形式で公開すること
- 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること
- 取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手し、成果を確実に蓄積していくこと
- 推進施策・体制
- 公共データ活用の推進
ニーズの把握、 提供方法等に係る課題の整理、検討、 民間サービスの開発 - 環境整備
公開ルール等の整備、データカタログ、データ形式・構造等の標準化推進等、提供機関支援等の検討 - 推進体制
各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議の下に電子行政オープンデータ実務者会議を設置
「電子行政オープンデータ戦略」は、この後、IT戦略本部により「新たなオープンデータの展開に向けて」(2015年)、「オープンデータ 2.0」(2016年)で、より具体化され、「官民データ活用推進基本法」(2016年成立)につながります。
世界最先端IT国家創造宣言(2013年策定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20130614/siryou1.pdf
2013年に、民主党から自民党への政権復帰があり、「新たな情報通信技術戦略」は「世界最先端IT国家創造宣言」に改訂されました。2020年までに、「世界最高水準のIT利活用社会を実現する」ことを目標にしたものです。
- 1.革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現
(1)オープンデータ・ビッグデータの活用の推進
(2)ITを活用した日本の農業・周辺産業の高度化・知識産業化と国際展開
(3)幅広い分野にまたがるオープンイノベーションの推進等
(4)IT・データを活用した地域(離島を含む。)の活性化
(5)次世代放送サービスの実現による映像産業分野の新事業創出、国際競争力の強化
- 2.健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会
(1)適切な地域医療・介護等の提供、健康増進等を通じた健康長寿社会の実現
(2)世界一安全で災害に強い社会の実現
(3)家庭や地域における効率的・安定的なエネルギーマネジメントの実現
(4)世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現
(5)雇用形態の多様化とワーク・ライフ・バランス(「仕事と生活の調和」)の実現 - 3.公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現
(1)利便性の高い電子行政サービスの提供
(2)国・地方を通じた行政情報システムの改革
(3)政府におけるITガバナンスの強化
体裁的には「i―Japan」の復活ともいえますが、「新たな情報通信技術戦略」の「国民本位」の施策や推進成果をほとんど取り入れています。「i―Japan」で試みた方向を、「新たな情報通信技術戦略」で具体的な施策にまで推進した結果を「世界最先端IT国家創造宣言」で実現しようという位置づけになるでしょうか。
この間に、「新たな情報通信技術戦略」の施策が法律として実現しました。
- 「国民ID制度」「公的ICカード」→「マイナンバー法」
- 「政府CIO制度の提言」→「政府CIO法」、IT戦略本部からIT総合戦略本部に呼称変更
- 「オープンデータ戦略」→「官民データ活用推進基本法」
この「官民データ活用推進基本法」を受けて、「世界最先端IT国家創造宣言」は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(デジタル・データ基本計画)に改訂されます。
マイナンバー法(2013年成立)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027
正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といいます。e-Japan戦略以来、行政内部でのシステム化、申告・手続きのオンライン化のためには共通個人番号の設定が重要だと指摘され続けてきたのですが、外部への漏洩や行政内部での不正利用などのセキュリティリスク、国民総背番号制による行政の監視などが問題になり、なかなか実現しませんでした。
しかし、自民党→民主党→自民党の政権交代が行われる間に、電子行政には個人番号が重要だの認識が広く合意されたのでしょうか、10年以上の紆余曲折の結果、成立になりました。
次には、マイナンバーの利用範囲が課題になります。成立には、セキュリティ等の慎重意見が重視され、かなり狭い用途に限定されています。反面、電子行政の積極的拡大の観点では、民間も含めた広範囲の利用を期待しており、どの範囲で合意されるかは未知数です。運転免許証、健康保険証のマイナンバー化が話題になっていますが、決着していません。
参照:「マイナンバー法」
政府CIO法(2013年成立)
正式名称を「内閣法等の一部を改正する法律」といいます
これまで、内閣総理大臣を本部長とするIT戦略本部が、国のIT戦略の中長期計画を策定し、推進してきましたが、この間にますますITは高度化し広範囲に影響してました。従来のIT戦略本部では、各府省のIT戦略を統合し成果を上げるガバナンス能力が不足してきました。
その対処のために、IT戦略本部をIT総合戦略本部と改称し、内閣情報通信政策監(政府CIO)という。政府の最高情報担当役員のような職制を設けました。
・内閣官房では内閣官房長官に次ぐ地位で、各府省政務官クラス(事務次官より上)の位置づけ
・IT総合戦略本部員としては国務大臣と同等の地位
・IT総合戦略本部の事務局であるIT総合戦略室の室長
とされているので、政府全体のIT政策及び電子行政の推進の司令塔として、府省横断的な権限を持ちます。
参照:「政府CIO法」
改正個人情報保護法(2015年月)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057"特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、個人情報を復元できないようにした「匿名加工情報」は、一定の条件のもとで第三者に提供できるようになりました。それによる様々なビッグデータを組み合わせて分析することにより、新規のビジネスが創出されたり、サービスの変化が得られる効果があります。2017年5月に全面施行されました。
参照:個人情報保護法
官民データ法(官民データ活用推進基本法)(2016年成立、2019年改正)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC1000000103
正式名称を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」といいます。
これまでに、オープンデータの活用について、IT戦略本部は「電子行政オープンデータ戦略」(2012年)、「新たなオープンデータの展開に向けて」(2015年)を提案してきました。それが法律として成立しました。
- 基本理念
情報の円滑な流通の確保、国際競争力の強化、新たな事業の創出、情報を根拠とする効果的かつ効率的な行政の推進などを基本理念としています。 - 行政の責務
推進のために、政府には活用推進基本計画の策定を求め、地方自治体には、地域における活用推進の施策についての基本的な計画を定めるよう努力義務を課しています。 - 基本的施策
オンライン利用の原則化、コンテンツ流通の円滑化、利用機会の格差の是正、研究開発の推進、人材育成、教育の振興の他、情報システムに係る規格の整備と互換性の確保を挙げています。 - 推進体制
IT総合戦略本部に官民データ活用推進戦略会議を設置し、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することとしています。
オープンデータ基本指針(2017年5月)官民データ活用推進戦略会議決定
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20190607/siryou10.pdf
「官民データ活用推進基本法」(2016年)を受けて、国や地方公共団体に対してオープンデータの推進に関する基本指針をまとめたもので、次のようなことを示しています。
- 行政保有データは原則オープンデータとして公開すること
- 公開データは数値データ、文章データを問わず二次加工が容易にできるようにすること
- パブリックドメインの利用規約に沿った公開をすること
- これらに伴う各種標準を採用すること
- 設計段階からオープンデータにすることを意図した措置を講じるオープンデータ・バイ・デザインの考え方に基づくこと
デジタル・データ基本計画(2018年策定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou5.pdf
正式には、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」といいます。
2016年に成立した「官民データ基本法」を受けて、従来からの中長期計画「世界最先端IT国家創造宣言」を改訂したものです。
「第1部 世界最先端デジタル国家創造宣言」は、従来からの「世界最先端IT国家創造宣言」の延長である
・行政サービスの100%デジタル化、行政保有データの100%オープン化
とともに、「官民データ活用推進基本法」との関係から、
・地方、民間部門のデジタル化
の切り口にしています。
「第2部 官民データ活用推進基本計画」は、「官民データ活用推進基本法」の「基本的施策(第十条―第十九条)」の具体的な推進方法を示しています。
デジタル・ガバメント実行計画(2019年策定)
IT総合戦略本部は、2017年~2010年に「デジタル・ガバメント」に関して次の方針・計画を発表しました。目的はどれも同じで、より深化させ具体的なものにしてきました。前の2つはIT総合戦略本部内部の決定ですが、最後のものは同本部の策定を閣議決定したものです。
- デジタル・ガバメント推進方針(2017年)官民データ活用推進戦略会議決定
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/suisinhosin.pdf - デジタル・ガバメント実行計画(2018年)eガバメント閣僚会議決定
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/densei_jikkoukeikaku.pdf - デジタル・ガバメント実行計画(2019年)閣議決定
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20191220/siryou.pdf
デジタル・ガバメントとは、行政電子化の戦略的運営というような意味です。単に手作業を電子化するのではなく、行政内部の合理化、民間との接点の効率化などを徹底するために、ITの利活用により、従来の制度や業務の方法を抜本的に改革しよう、すなわちBPRを推進しようということです。
これは、eーJapan戦略以降、常に言われてきたことですが、各種法律の未整備やIT総合戦略本部の弱体などにより実現できませんでした。それが、この5年間の間にBPRを行う環境が整ってきたので、改めて推進を促進しようという計画です。
「2017年版」では「デジタル・ガバメント」が重要であり、規制制度改革との連携による行政手続・民間取引IT化に向けた「デジタルファースト・アクションプラン」を提唱、そのなかで「デジタルファースト」「ワンスオンリー」「コネクテッド・ワンストップ」の3原則を掲げました。
「2018年版」でのeガバメント閣僚会議とは、政府CIOと各省閣僚による電子政府改革の会議組織で、後に「デジタル・ガバメント閣僚会議」に改称しました。すなわち、本計画は各省庁のトップにより合意された実行計画だといえます。ここでは、「利用者のニーズから出発する」「事実を詳細に把握する」などの「サービス設計12箇条」を発表しました。これは、BPRを基盤とした利用者中心の行政サービスのプロジェクトを成功に導くノウハウで、デジタルファースト・アクションプランの推進原則だともいえます。
「2018年版」は、これらを受けて、総合的な推進計画にしたものです。あるべき姿を「必要なサービスが、時間と場所を問わず、最適な形で受けられる社会」「官民を問わず、データやサービスが有機的に連携し、新たなイノベーションを創発する社会」であるとし、「DigitizationからDigitalizationへ」の観点移行、BPRの推進などが示されています。
デジタル手続法(2019年成立)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000151
正式名称を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」といいます。上記の「デジタル・ガバナンス」のうち、オンライン申請・手続きの分野を対象に、国や地方公共団体の責務などを定めています。
- 申請・手続きの基本原則
「デジタルファースト」「ワンスオンリー」「コネクテッド・ワンストップ」の3原則です。 - 原則オンライン
行政手続きは原則オンラインであること(本人確認や手数料納付などもオンライン)、他の行政手続きで作成した書類は他の手続きでは添付不要など。 - 民間システムとの連携
例えば引越時の行政手続きで、電気やガスなどの事業者への手続きも完了するなど - 安心・安全
高齢者等の相談窓口などデジタルデバイドの是正、情報セキュリティ対策の強化など
参照:「デジタル手続法」
デジタル庁設置以降
デジタル改革関連法(2021年成立)
これまでの経緯
- ITの利活用による行政内部の合理化、申請手続きの利便性、行政データのオープンデータ提供などは、国のIT戦略の重点計画として推進されてきた。→各中長期戦略、官民データ法、デジタル手続法
- これらのシステムは、個人番号を用いるシステムが多い。統一個人番号としてマイナンバーが設定されたが、個人情報の保護などとの兼ね合いなどから、その適用範囲が限定されている。安全・安心を確保しつつ適用の拡大を図ることが重要だと指摘されてきた。→改正個人情報保護法
- それには、各府省、地方公共団体を統合した総合的なアプローチが必要である。その担当組織である内閣官房のIT総合戦略本部があるが、そのガバナンスを強化する必要があると指摘されてきた。→政府CIO法
コロナ対応での反省
2020年からの新型コロナウイルスの大流行は、社会の広い分野に深刻な打撃を与えました。それに迅速に対応すべき行政のITシステムや関連環境の欠陥が多いことが顕在化しました。
- 全国民に10万円の給付金配布において、オンライン申請に使われたマイナンバーカードのシステムの未整備などで、オンライン申請者のほうが給付が遅れてしまった。
- ワクチン接種の予約システムが自治体ごとに異なり各地で混乱した。「国がインフラとして整備していれば防げた可能性が高い」「標準化により自治体の負担が軽減されれば別の対面サービスに予算や人を充てられる」と指摘された。
- 多様な給付金や支援金の振込先を、申請者がその都度指定する必要があった。マイナンバーを振込先の預貯金口座とひも付ければ、自動的な振込みが可能になり、給付までのタイムラグが短縮できる。
- 企業ではテレワークが行われたが押印手続等の阻害要因が顕在化、学校ではオンライン授業が行われたが、必要な基盤やノウハウの不足が顕在化した。
コロナの影響はあまりにも大きく、収束した後でもコロナ以前の社会には戻らず、ニューノーマルな社会に移行するとされ、それに対応するにはITの高度利用による「デジタル強靭化社会」を実現するための国の積極的な推進戦略が期待されます。
このような動向や反省により、2021年に「デジタル改革関連法」が成立しました。次の6法律の総称です。
・デジタル社会形成基本法(IT基本法の後継)
・デジタル庁設置法(IT総合戦略本部からデジタル庁へ)
・デジタル社会形成整備法(多数の関連法律(主に個人情報保護法、マイナンバー法)の改正、押印不要化
・公金受取口座登録法(マイナンバーとの紐づけ)
・預貯金口座管理法(同上)
・自治体システム標準化法(システムの統一)
デジタル社会形成基本法(2021年成立)
デジタル社会に向けた政府の基本理念や施策策定の基本方針などを定めて、国や地方、事業者の「デジタル社会形成」を推進する責務を規定したものです。
・IT基本法の廃止
・デジタル庁の設置
が定められています。
- 基本理念
「デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念を規定する。」 - 施策の策定に係る基本方針
「デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保(データの標準化等)、アクセシビリティの確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨を規定する。」
参照:デジタル社会形成基本法
デジタル庁設置法(2021年成立)
「デジタル社会形成基本法」を設置根拠とする、国のデジタル政策を立案し、各府省・地方公共団体のデジタル化の司令塔としての機能をもつ組織です。
組織の概要
- 同庁の長は内閣総理大臣。デジタル庁担当大臣を置く。
- 事務次官相当のデジタル監を民間から登用する。従来の政府CIOに相当
- 職員500人規模。約120人を民間登用する方針。各省庁の出向者を受け入れる。
- 全国務大臣等を議員とする、デジタル社会推進会議を設置する。
主な機能・権限
- 内閣補助事務として、デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案・総合調整を行う。
- 総合調整機能を強化するため、他省庁への勧告権の付与、関連予算の一括計上などの権限を持つ。
- 分担管理事務として、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成及び推進を行う。
マイナンバーの利用、オンライン本人確認、オープンデータ提供、国・地方公共団体情報システムの標準化など
参照:デジタル庁設置法
デジタル社会形成整備法(2021年成立)
正式名称を「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」といいます。多くの関連法律の改正を一括したものですが、主な対象は「個人情報保護法」と「マイナンバー法」の改正です。
- 個人情報保護法の改訂
- 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法を、ほぼ個人情報保護法に合わせて一本化する。
- 個人情報の定義を個人情報保護法の「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個⼈を識別することが できることとなるものを含む」に統一。「匿名加工情報」は非個人情報とする。
- 公的部門にも匿名加工情報・仮名加工情報の識別行為禁止義務等を適用し、それらを非個人情報として利用することを法令の定める所掌事務の範囲内で認める。
- これまで学問研究での保護義務を全体として対象外にしていたのを、学問研究の分野に応じて対象内/外を定める。
- マイナンバー法の改正関連
- マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化として、次のような改正をしています。
- 郵便局事務取扱法:郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする。
- 公的個人認証法:本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする。
- 住民基本台帳法:転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける。
- マイナンバー法:電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能にする。
- その他:各種手続について押印を不要とする。
公金受取口座登録法、預貯金口座管理法(2021年成立)
給付金支給などを簡便に短期間で行えるインフラとして、マイナンバーと預貯金口座をひも付けできるようにする法律です。ひも付けは本人の同意が前提となります。
- 公金受取口座登録法(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律)
「公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあらかじめ登録し、行政機関等が当該口座情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給のためマイナンバーを利用して管理できることとする。」 - 預貯金口座管理法(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律)
「デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度を創設する。」
自治体システム標準化法(2021年成立)
自治体システムは、原則として各自治体が独自にベンダに発注し開発していたため、開発・運用コストがかかるし、自治体間の情報共有が円滑にできないなどの課題がありました。クラウドコンピューティングやソフトウェアの部品化・再利用の技術の発展やデジタル社会形成整備法による法的制限の解消など、システムを標準のルールやインフラで構築する環境が整ってきました。
自治体が2025年度までに、国が定める標準仕様に対応した基幹系システムへ移行するよう義務付けるとしています。また、デジタル庁がが提供する予定のクラウドコンピューティング環境(Gov-Cloud)の利用を推奨しています。
参照:自治体システム標準化法